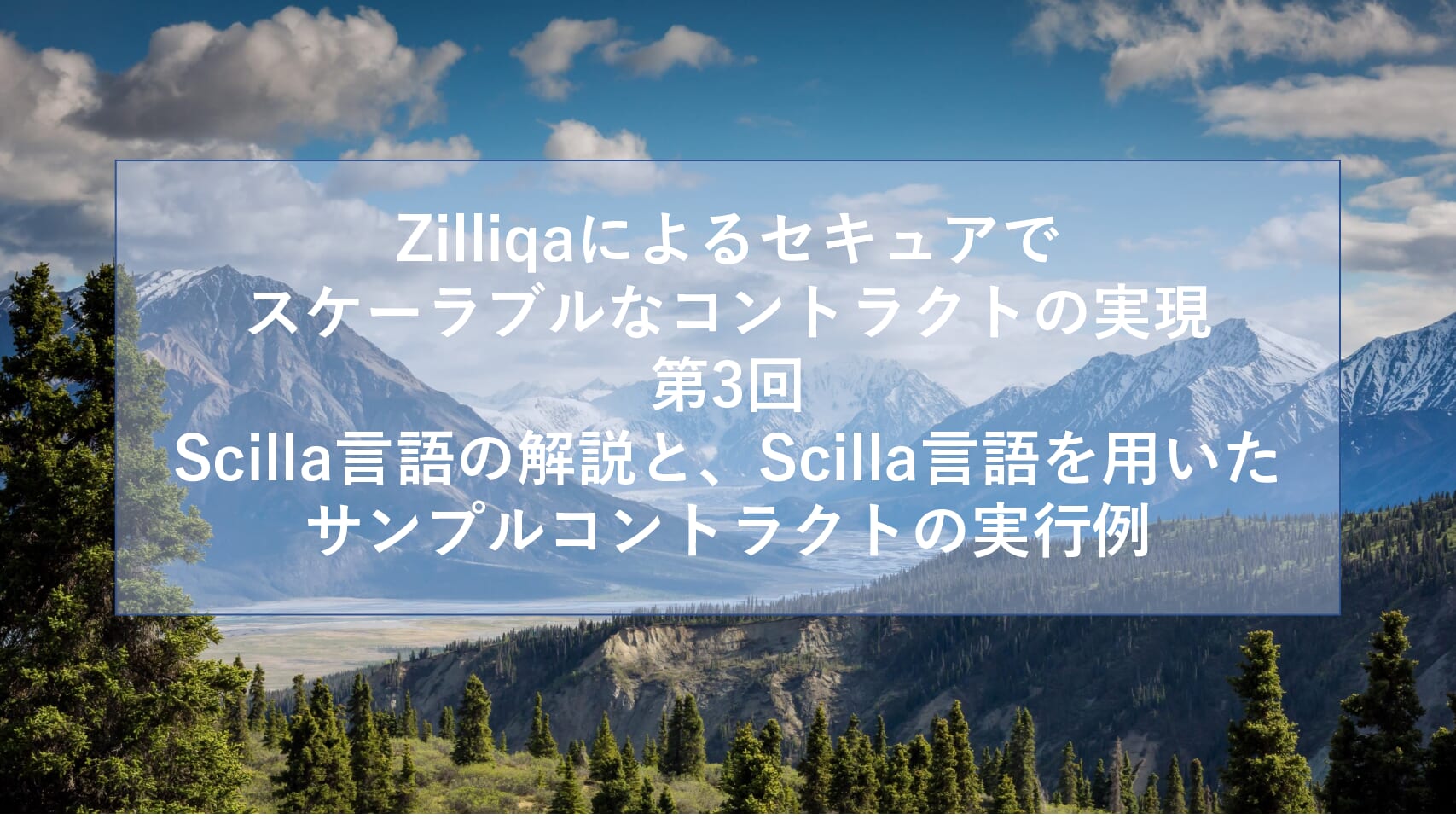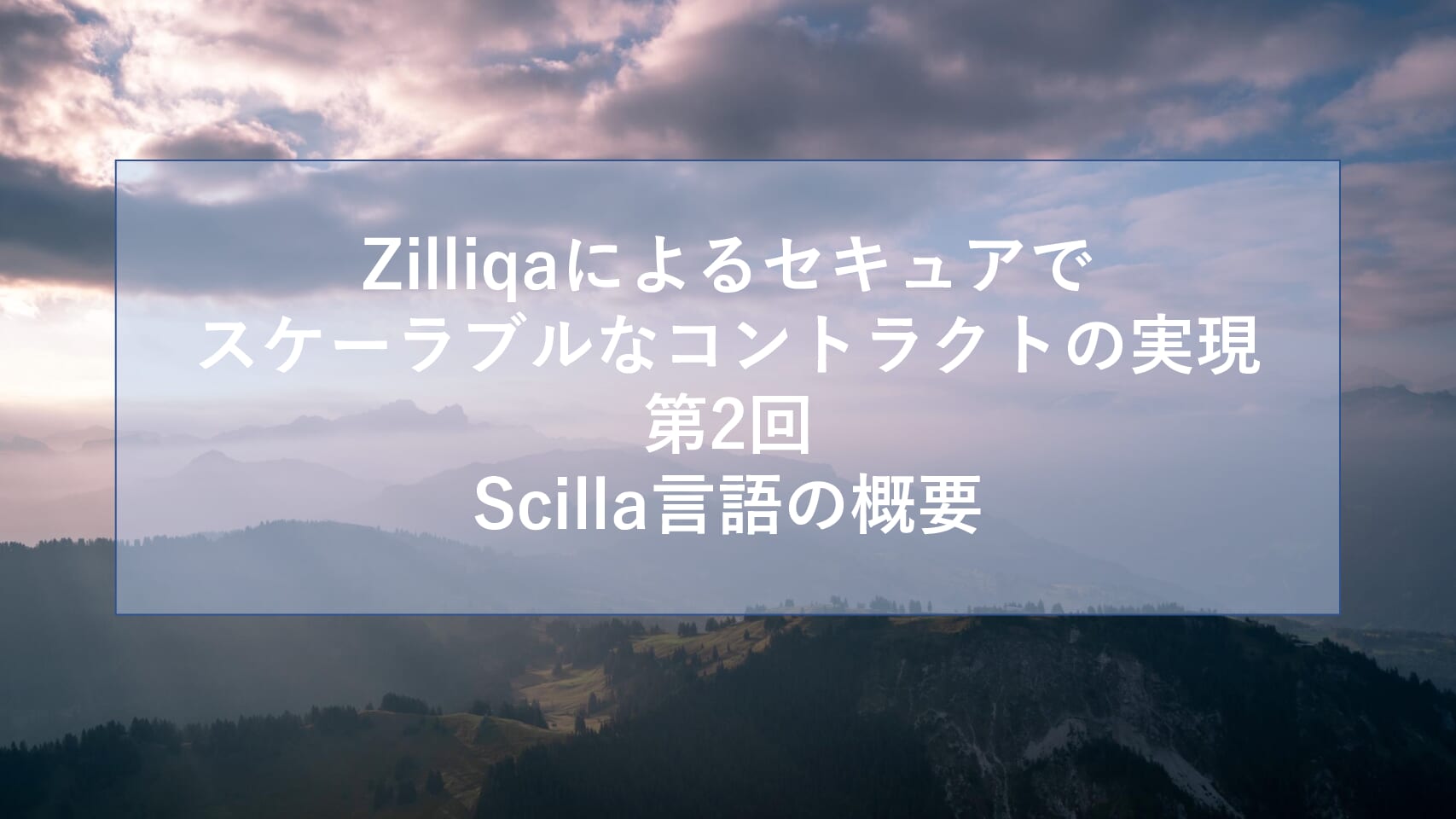はじめに
DeFiの分散レンディングは、DeFiというムーブメントが起こった最も大きな要因だと考えられます。そもそもDeFiという言葉が生まれる以前からDEX/流動性プロトコルのエコシステムは既に存在していました。しかし、MakerDAOを筆頭としたレンディング・プロトコルが、ETHホルダの資産運用先として大きな注目を集めるようになった頃から、「Ethereum上の分散的な金融サービスが各分野で隆盛してきた」と捉えられるようになり、DeFiという言葉で括られだしました。
本記事は現在のDeFiエコシステムの中で最もホットな領域であるレンディングに焦点をあてた内容となります。
DeFiの分散レンディングの概要
レンディングとは債務・債権を生み出す金融契約のことです。従来では、銀行融資や消費者金融のおけるローン、フィンテック領域ではP2Pレンディングといったような前例があります。しかし、DeFiの分散レンディングは従来のシステムとは根本から異なります。それは、これらのサービスがブロックチェーン上にあり、スマートコントラクトによって動作するためです。
・メリット・デメリット
DeFiの分散レンディングのメリットを述べると、主に3つに分類されます。トラストレス
一つ目はトラストレスだという点です。スマートコントラクトはあらかじめ定められた取引内容を、サードパーティーに依存することなく自動で執行します。したがって、ユーザーは中央集権的な機関を信頼することなく、オンライン上で見知らぬ個人同士で金融取引を行うことができます。これは透明性という言葉でも表すことができます。パーミッションレス
二つ目に、パーミションレスだという点です。現段階では、DeFiのレンディングサービスは、スマホを持ちインターネットにアクセスさえできていれば世界中誰でも利用することができます。KYCが存在しないため、面倒な書類手続きも、未成年だからといって排除されることもありません。オープンソース
三つ目に、DeFiのプロトコルとアプリケーションは、オープンソースであるという点です。これによりサービス同士の連携は容易になり、多様なモデルのサービスを生み出すエコシステムを作ることができます。加えてオープンソースであるというのは、透明性を証明することにも繋がります。・レイヤー構造
先ほどからプロトコルとアプリケーションという2つの言葉が出てきていますが、この言葉はDeFiのレンディング・エコシステムのレイヤーを区別するために使われます。以下の画像をご覧ください。最下層にはEthereumブロックチェーンがあり、二層目にはミドルウェア・プロトコルという、オープンに共有可能なスマートコントラクトを提供するプロジェクト群が位置しています。そして最上層にはミドルウェア・プロトコルのスマートコントラクトを活用したアプリケーションを提供するプロジェクト群があります。
下記にて、上位二層の違いと具体的な事例について解説していきます。
DeFiの分散レンディングのプロジェクト紹介
・ミドルウェア・プロトコル
先述の通り、ミドルウェア・プロトコル層はオープンソースで提供されるスマートコントラクトを開発するプロジェクトがあります。・MakerDAO
*MakerDAOとDAIの基本的な仕組みについては、前回の記事をご覧ください。
・Compound
そしてミドルウェア・プロトコルでもあるので、Compoundのスマートコントラクトを活用したアプリケーションもいくつか存在します。(※後述)
具体的には、ユーザーはCompoudのスマートコントラクトに対し、Supply(貸し)という形でいくつかのトークンをデポジットすることで、利息を得ることができます。
一方、その収益はどこからきているのかというと、CompoudのスマートコントラクトからBorrow(借り)という形でトークンを借りるユーザーが支払う金利から発生しています。
この仕組みは一般的な銀行の事業モデルに似ています。現在の日本はマイナス金利なので銀行預金で利子を得ることは難しいですが、例えばCompoudでDAIを貸し出すと年利で3~7%の利益を得ることができます。
・Dharma

エスクロー(第三者預託)サービスは、デジタル上で信用し合っていない個人同士が行う方式のため、トラストレスなスマートコントラクトの得意分野だと言えます。Dhamraのようなモデルは長期的に見て大きな影響力を持つと考えられます。
Dharmaは現在自社でアプリケーションを開発していますが、元々はミドルウェア・プロトコルとして始まったプロジェクトでもあります。Dharmaの開発陣は、将来的にはDharmaの上にP2Pレンディング・アプリケーションや債券発行プラットホームが誕生すると考えています。
・アプリケーション
以下では、上記3つのミドルウェア・プロトコルを活用して作成されたアプリケーションについて解説します。・Bloqboard

・InstaDApp

BloqboardはDeFiレンディングを行いたい投資家にとっては、全てのスマートコントラクトに一度にアクセスできるため非常に利便性が高いです。このような水平的なインターオペラビリティ(相互運用性)はこれからも他の領域で増加していくと考えられます。
また、InstaDAppはMakerDAOのCDPの利便性を高めるために、独自の機能や流動性プロトコルを活用し、垂直的なインターオペラビリティも実現しています。