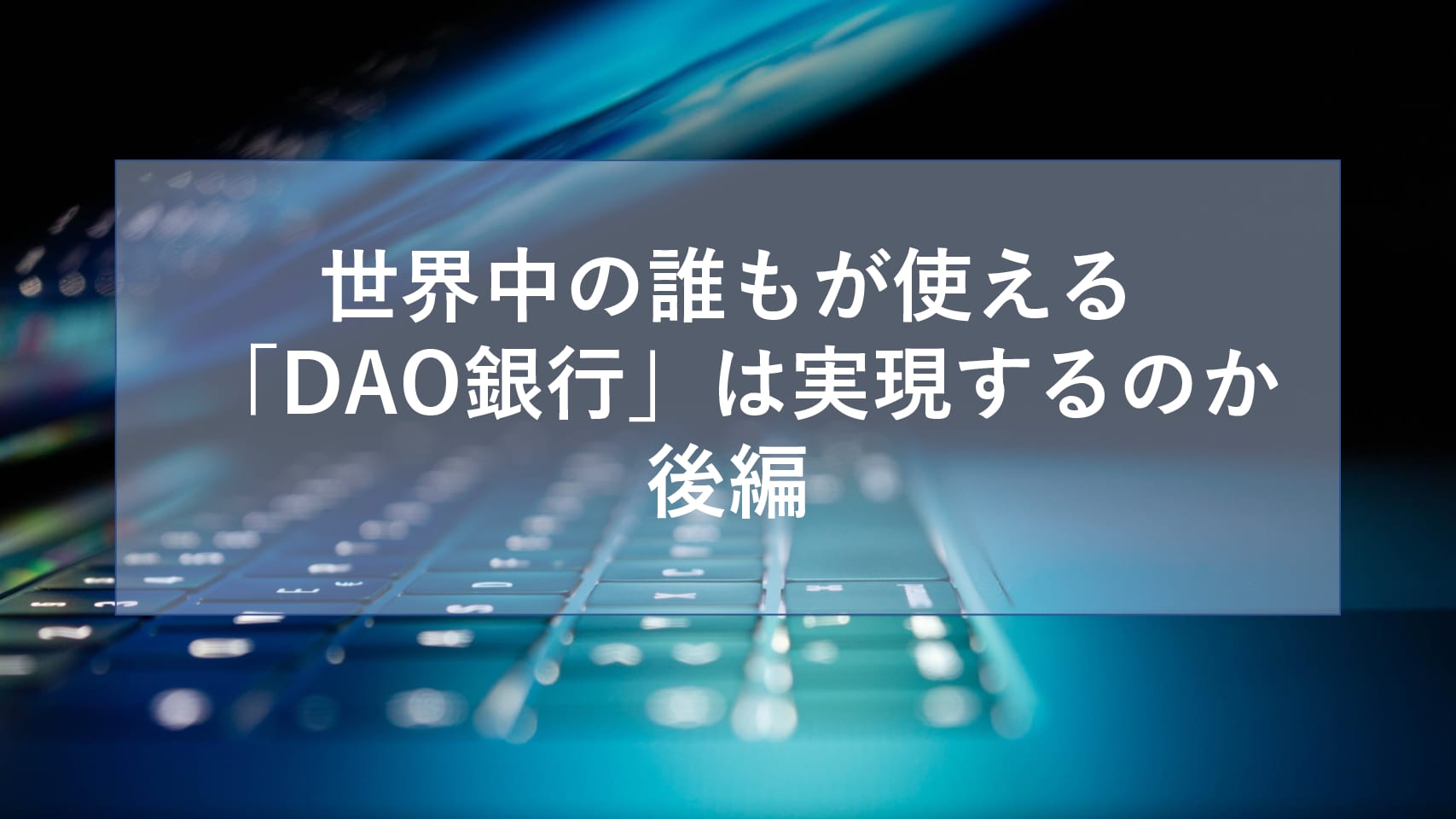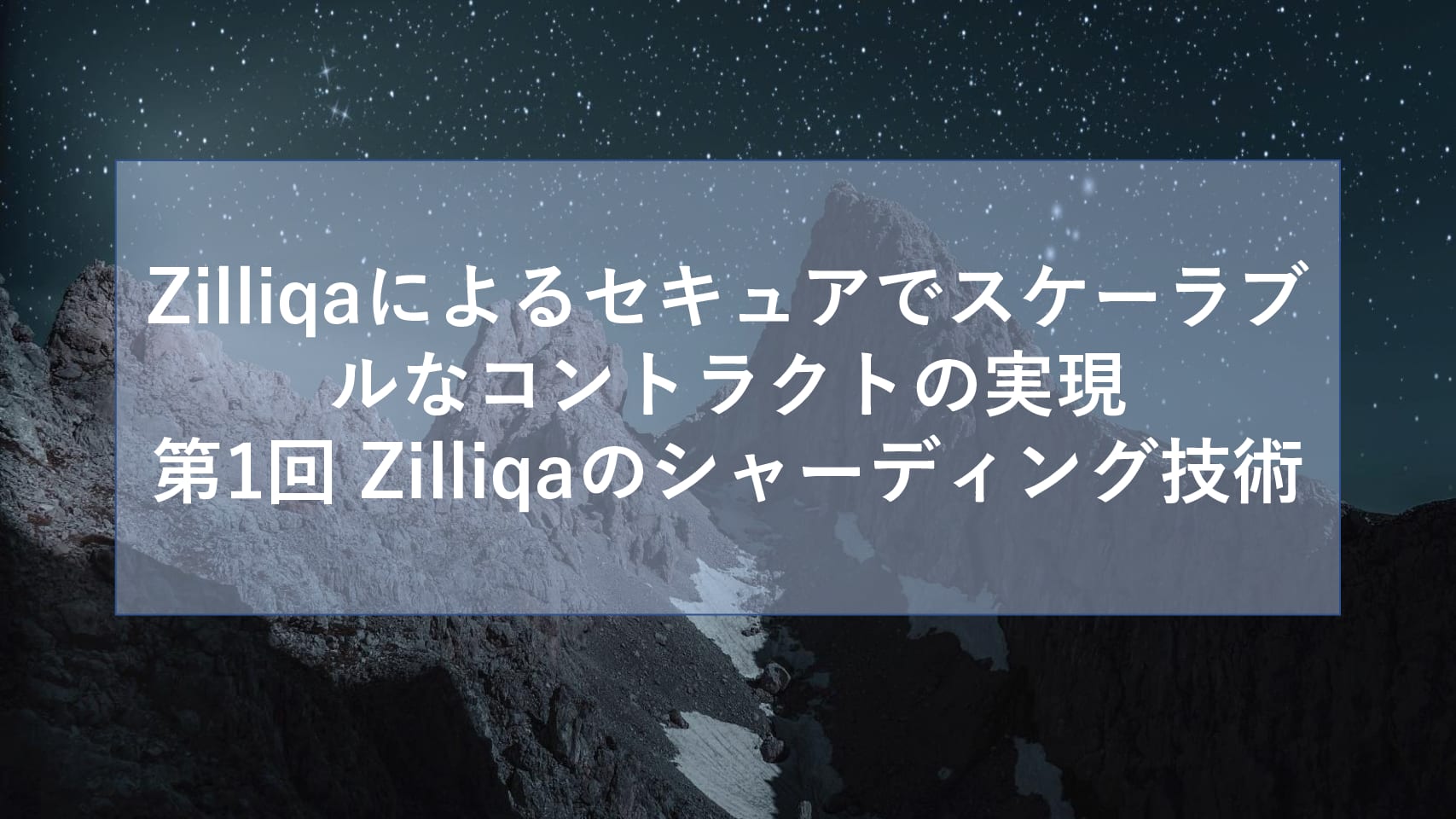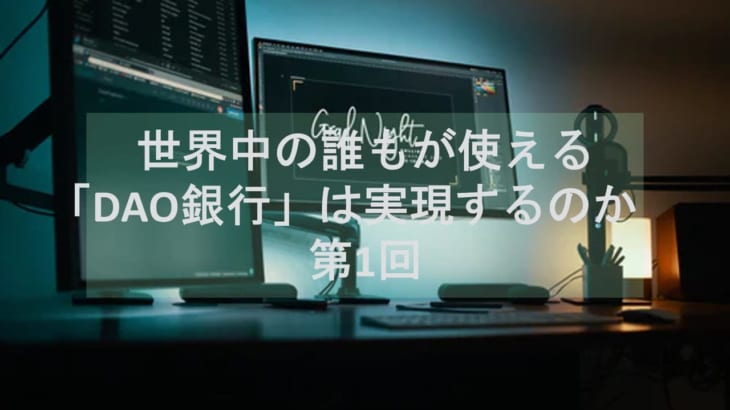はじめに
本記事は、過去にコンセンサス・ベイスが主宰していたオンラインサロンの記事です。記事は2017年~2018年にかけて執筆されたため、一部は、既に古くなっている可能性があります。あらかじめご了承ください。
今回の内容
本連載では、2018年2月に提案されたRe-Fungible Tokenと呼ばれる新しいトークンのアイデアについて全2回で解説します。
第1回では、Re-Fungible Tokenの理解の前提として、Cryptoeconomicsやさまざまなトークン規格の類型や登場の背景、Re-Fungible Tokenの応用可能性について解説します。
第1章 Re-Fungible Tokenとは
Re-Fungible Token(RFT)とは、2018年2月にBilly Rennekampにより提案された新しいトークンのアイデアです。Ethereumのトークン規格であるERC20やERC721を拡張して設計されていますが、まだERCとして標準化されているものではありません。
Re-Fungible Tokenの目的は、アート作品や知的財産への貢献に対して、経済的に正当な報酬を与えることで、文化や技術の成長を後押しする小規模な経済圏を実現することです。
これまで、無名のアーティストが新しい作品を発表するためには、スポンサーやパトロンの協力が不可欠でした。音楽家が新しい曲を発表して収益を上げるには、数ヶ月から数年かかることもあり、その間の経済的な保障がありませんでした。
また、アート作品の販売は、レコーディング会社や広告代理店などによる中央集権的な構造から、ソーシャルメディアやインフルエンサー、キュレーターなどの不特定多数の参加者による非中央集権的な構造に変化しつつあります。
こうした不特定多数の参加者に対して、影響力に応じた正当な報酬を与えることで、よりアート作品の拡散をしやすくしたり、芸術家や協力者の経済的な保障を行えるようにするアイデアの一つが、Re-Fungible Tokenです。
類似アイデア
Re-Fungible Tokenの類似アイデアとして、Nuhanse Network社によって同じく2018年2月にホワイトペーパーが発表されたQuobandsがあります。
Quobandsは、主に土地や家屋などの物理的な資産を複数人で所有しあう「所有経済(Ownership Economy)」の実現を通じて、住宅価格の適正化や都市開発の支援などを目指すプロジェクトです。
Cryptoeconomics
Re-Fungible TokenやQuobands以前にも、証券や株式、クラウドファンディングなどの方法で、アート作品制作の費用を募るものや、物理的な資産の所有権を分割するものは存在していました。
しかし、それらの既存システムは、円やドルなどの法定通貨に依存する経済圏で実現されていました。
ブロックチェーン技術の登場以降、ビットコインに代表される暗号通貨によって、既存の法定通貨による経済圏に依存しない新しい経済圏が実現できることが実証されました。
暗号通貨による経済圏は、あらゆる価値や資産が電子化され、それがインターネットを通じて即座に取引され、プログラムにより自動的に処理できるものであり、流通コストや人的コストを大幅に削減したり、盗難や災害などのリスクを低減させるものとして期待が高まりました。
さらに、Ethereumの登場により新しい経済圏をプログラムするためのプラットフォームが登場したことで、誰もが新しい経済圏を設計し、実現することが可能となり、さまざまな技術競争が加速しています。
このような、暗号通貨技術を用いた新しい経済圏の設計や実現は、Cryptoeconoimcsやトークンエコノミーと呼ばれています。
そして、このCryptoeconomicsで最も重要な役割を果たすものが、トークンと呼ばれるユニットです。
Re-Fungible Tokenを説明する前に、現在のトークンの概要について振り返ってみましょう。
第2章 トークンの類型
暗号通貨システムにおいて、トークンという言葉はさまざまな意味に用いられています。
技術的な観点では、既存のブロックチェーン上で発行された独自のコインがトークンと呼ばれます。
一方、経済的な観点では、人々が価値を感じるあらゆる資産をブロックチェーン上でデジタル化したものがトークンと呼べるでしょう。
最初にイメージしやすいトークンは、特定の目的や特定のサービス内で地域通貨のように利用できる、貨幣としてのトークンです。
例えば、P2P型のストレージシェアリングサービスであるStorj内で、ストレージリソースの貸し借りのための利用されるSTORJトークンや、実店舗における決済サービスであるOmiseGoで利用されるOMGトークンなどです。
もちろん、暗号通貨が登場する以前にも、特定のサービス内で使えるポイントや、ゲーム内コインなどは存在していました。
しかし、それらの通貨はサービス終了とともに無価値となってしまうものだったのに対し、ブロックチェーンを用いたトークンは、ユーザーの持ち物としてブロックチェーン上に記録され、他の人に譲渡したり、他のトークンと交換したりすることができます。ブロックチェーン技術への期待の高まりとともに、トークンを用いた新しいサービスの提案や開発が急速に進められました。
ERC20
新しいサービスで利用する新たなトークンを実装することは、技術的に難しいことではなく、そのサービスの特徴に応じてさまざまな改良を加えたトークンを開発することも可能です。
しかし、それぞれのサービスで全く独自のトークンが実装されてしまうと、そのトークンを扱うためのウォレットや、異なるトークンを交換するための取引所システムなどの設計が非常に複雑になります。また、思わぬバグや脆弱性が混入するリスクも高まります。
そこで、さまざまなトークンを統一的に扱えるようにするため、トークンの標準規格が求められました。
ERC20は、Ethereum上で新しいトークンを発行するための最初の標準規格です。
ERC20には、さまざまな種類のトークンで一般的に必要と思われる機能のインターフェイスを定義しており、この定義に沿って新しいトークンを実装することで、ウォレットや交換所などのシステムが統一的に新しいトークンを扱うことができるようになります。
ERC223
ERC20には、さまざまなトークンで汎用的に必要となる最低限の機能が定義されており、ERC20トークンが普及するにつれ、それらの機能だけではさまざまな問題が発生することが分かってきました。
最大の課題は、トークンを誤って送付してしまった場合のチェック機構がなく、トークンの消失が起こりやすい点です。
ERC223は、トークンの送付先を間違えてしまった場合に、トークンを送り主に送り返すFallback機能を定義しています。
Fungible Token
上で見たERC20やERC223などのトークンは、それぞれのアカウントにどれだけトークンの残高が存在するか、という形でトークンの所有を表現しています。
したがって、アリスが100トークン、ボブが100トークンを持っていたとすると、両者のトークンの価値は全く同じです。
また、トークンの量は、発行する際に任意の粒度まで分割することができます。
日本円などを現金で取引する場面では、なかなか1円未満の取引をすることはありませんが、トークンの場合は0.00001トークンを送る、といったことも可能です。
これまで、貨幣として流通してきた米や小麦、金や銀なども、同様に重量で計量され、価値の尺度や交換の手段として用いられてきました。
このように、価値が分割可能な量で表現され、それぞれの実体の区別をしなくてもよい特徴を、経済学ではFungibility(代替可能性)と呼び、Fungibilityを備えたトークンはFungible Tokenとも呼ばれます。
ERC20やERC223などは、このFungible Tokenの一種です。
Non-Fungible Token (NFT)
Fungible Tokenに対して、代替可能性のないトークンとしてNon-Fungible Tokenがあります。さきほど説明したとおり、Fungibilityは通貨としては重要な特徴です。なぜ、あえてその特徴をなくすようなトークンが必要なのでしょうか?
トークンの目的は、人々が価値を感じるあらゆるものをデジタル化することです。人は、通貨以外にも価値を感じるものがあり、その中には替えのきかない唯一の価値も有りえます。
例えば、アリスが持っている200万円の価値の車を、ボブに貸したとします。ボブは一週間後に、同じく200万円の価値がある別の車を返したとしたらどうでしょうか?
アリスにとっては、自分の所有していた車は唯一無二のものであり、金銭の尺度で測れるものではありません。
このような、車や土地、家屋、アート作品など、替えのきかない唯一無二の資産をトークンとして表現するものとして、Non-Fungible Tokenが登場しました。
Non-Fungible Tokenは、多くの場合一つの資産と一つのトークンが1対1で紐付いており、それ以上分割することはできず、一つのトークンに対してただ一人の所有者を設定することができます。
Ethereumでは、Non-Fungible Tokenのトークン規格として、ERC721があります。
Re-Fungible Token (RFT)
Re-Fungible Tokenは、分割不可能であったNon-Fungible Tokenを、再度分割して譲渡可能にするという新しいトークンのアイデアです。
もともと、Divisible non-fungible tokens (Shared ownership over NFTs)というタイトルでEIP上で議論されたものが発端となっており、こちらのタイトルのほうがより実体を正確に表現しているものと言えます。
Re-Fungible Tokenのアイデアは、Non-Fungible Tokenの所有者を特定の人ではなく、Fungible Tokenを実装したコントラクトにしてしまうというものです。
詳細な実装については、第2回の記事で解説します。
第3章 Re-Fungible Tokenの応用可能性
これまでも、アート作品などをトークンとして表現する例はありました。デジタルなアート作品は無制限にコピーができてしまうため、トークンとしてコピー不可能な電子データとして流通させるというものです。
アート作品としての写真や版画などは、写真のネガや版木が残っていれば無制限に作品を製造できてしまうため、一定数の写真や版画を作成したあとは、ネガや版画を物理的に破壊して作品としての希少性を担保する、ということが行われていました。
これと同様に、あるアート作品の所有権を一定数のトークンとして発行し、流通させることが可能です。
しかし、既存のトークンの仕組みを用いてアート作品を流通させる方法は、いくつか問題があります。
Non-Funbible Tokenの課題
まず、Non-Fungible Tokenとしてアート作品の所有権を発行してしまうと、そのトークンの所有者が一人に限定されてしまいます。世界に一点しか存在しない物理的な作品の所有権を表現する場合にはそれでも良いかもしれませんが、写真や音楽などのデジタル作品を多くの人に届けたいといった場合には使えません。
写真や音楽などのデジタル作品に1~2000などの通し番号を付けて、それぞれをNon-Fungible Tokenとして流通させることも可能ですが、個々のトークンの独立性が高いNon-Fungible Tokenでは、個々の作品をオークションのような形で取引することになり、流通に手間がかかります。
一般的に、ある音楽のCDを買いたいときでも、「あのCD」と「このCD」を区別して考えることは少ないでしょう。このような資産は、Fungibleなものとして扱われるほうが自然です。
Fungible Tokenの課題
一方、上記のトークンをFungible Tokenとして実装した場合でも、いくつかの問題が発生します。
まず、アート作品の所有権の価値を保証するために、トークンの発行量に上限を設ける必要がありますが、アート作品の価値が事前に分からないうちに、発行量を見積もることは難しいでしょう。また、作品の需要は作品の認知によって変化しうるので、需要の変化に対して供給が一定となってしまうトークンでは、価格が不安定になりがちです。一部の投資家がトークンを買い占め、あとから不当な価格設定で売りつける、といったことも起こり得ます。
これまでのトークンモデルは、通貨や物理的に存在する資産をデジタル化することは可能でしたが、アートや知的財産などの抽象的な資産をモデリングするには不十分でした。
Re-Fungible Tokenのアイデアは、こうした既存のトークンでは対応しきれなかった種類の資産をトークン化し、健全な価格決定や正当な報酬の分配に有効ではないかと考えられます。
次回は、Re-Funbile Tokenの具体的な実現方法や、その考察について紹介します。
以上。
参考文献
- Re-Fungible Token (RFT) https://medium.com/@billyrennekamp/re-fungible-token-rft-297003592769
- Ethereum上のトークン類型と新アイデア「Re-FungibleToken」について https://magazine.ginco.io/post/topic_refungibletoken/
- ERC721 Non-Fungible Token Standard https://github.com/ethereum/EIPs/blob/master/EIPS/eip-721.md
- Quobands: A Funding Mechanism for Crowd Construction https://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=3107645